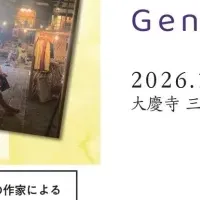

フィンランド学者が静岡のマザー工場を初訪問し技術を探る
産官学の連携が生んだ静岡のものづくりの未来
2023年の初夏、静岡県静岡市に位置する駿河生産プラットフォームが、フィンランドの著名な大学教授やグローバルな製造業者、コンサルタントらで構成される視察団を迎えました。この視察は、フィンランド政府が推進する「デジタル・グリーン・サプライチェーン」を深く理解することを目的としています。
視察団の背景と意義
フィンランドでは、産業のデジタル化とサステナビリティが現在の国家戦略の核心を成しています。今回の視察団は、統合型ものづくり研究の先駆者である早稲田大学の藤本隆宏教授の推薦によって細かな生産モデルを学ぶために日本を訪れました。その目的は、駿河生産プラットフォームが誇る「変種変量の自働化」技術の理解を深め、特に多様な商品を迅速に提供できるデジタル生産モデルに注目することです。
工場内の視察と技術の紹介
視察団は、まずミスミグループの生産技術の全体像についての説明を受け、その後製造現場を訪問しました。特に注目されたのは、「ALASHIスタジアム」と名付けられた自社開発の金型研削システムです。こちらはミクロン単位での精密加工が可能で、少量多品種の変種変量生産を実現しています。これにより、非常に高い精度が求められる金型部品の生産性とクオリティが飛躍的に向上しています。
また、無人生産を実現する「meviyデジタルマニュファクチュアリングシステム」も紹介されました。これにより、AIを活用して製品設計から生産までを効率化し、迅速な納期を実現しています。meviyは、「第9回ものづくり日本大賞」で内閣総理大臣賞を受賞するなど、その革新性が高く評価されています。
視察の構成と反響
2025年9月16日には、短時間で大きな進化を遂げた駿河生産プラットフォームの技術が披露され、多くの注目を集める予定です。視察後、ヨハン・ヴァリン博士は工場の進化に感銘を受け、デジタル技術が物の流れと融合している様子に驚きました。また、駿河生産プラットフォームの代表取締役社長である遠矢工は、この視察を通じて日本のものづくりが国際的に評価されていることをアピールしました。
異文化交流と技術革新の重要性
駿河生産プラットフォームは、2005年に株式会社ミスミグループ本社との経営統合を経て、精密加工技術を駆使し、世界中に展開する製造業の中核を果たしています。全世界で培った経験に基づく高度な技術とノウハウは、今後の国際的なビジネス展開にもつながる重要な資産となるでしょう。
未来のものづくりの形は、まさにデジタル技術による変革の中で進化しています。フィンランドとの連携は、その先駆けともなり、今後の国際的な視点からも注目されることでしょう。









関連リンク
サードペディア百科事典: ものづくり フィンランド 駿河生産プラットフォーム
トピックス(その他)
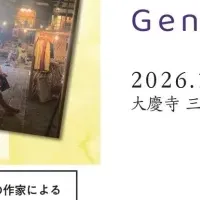

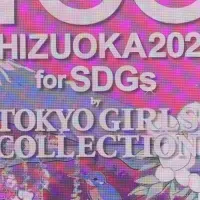
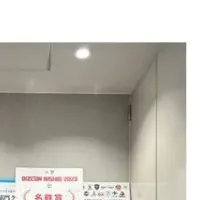

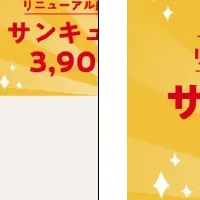




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。