

くら寿司と海と日本プロジェクト共同の「お寿司で学ぶSDGs」出張授業が宍道小学校で開催決定
くら寿司×海と日本プロジェクトが贈る出張授業
2025年11月13日、島根県松江市にある宍道小学校で、くら寿司と一般社団法人海と日本プロジェクトinしまねが共同で「お寿司で学ぶSDGs」という出張授業を開催します。このプログラムは、海洋環境や食品ロス、さらには漁業資源の大切さを子どもたちに学ばせることを目的としています。授業では、児童たちが実際に参加した体験学習の様子を収めた動画を視聴し、地域の漁業の現状や海の恵みについて理解を深めることが期待されています。
背景と目的
近年、漁業資源の減少や食品ロスの問題は深刻さを増しています。こうした問題点を解決するための行動を考える際、子どもたちが主体的に関わることが重要です。子どもたちに「海の恵み」を未来にどうつなげるかを考えさせるこの授業は、SDGsにおける目標12(つくる責任 つかう責任)や目標14(海の豊かさを守ろう)、目標17(パートナーシップで目標を達成しよう)に沿った内容で構成されています。実際に行われる「お寿司屋さん体験ゲーム」や「課題解決ワークショップ」を通じて、楽しみながら学ぶ機会を提供します。
授業の内容
この出張授業は、3部構成で行われます。まず、海洋資源が抱える現状について「未来ではお寿司が食べられなくなる!?」というテーマの下、映像と魚の模型を用いて説明します。漁業が直面する資源の減少や担い手不足、気候変動の影響などを子どもたちが理解できるように工夫されています。
次に、「お寿司屋さん体験をしよう!」のコーナーでは、くら寿司が考案したオリジナル教材を使用し、実際にお寿司を提供する体験を通じて、食品ロスや資源の有効活用について学びます。この体験を通じて、児童たちは過剰提供や廃棄の問題についても実感を持って理解することができるでしょう。最後は、グループで意見を出し合いながら「どうすればお寿司を未来にも食べ続けられるか」というテーマで解決策を考える時間が設けられます。低利用魚の活用方法やICTを通じた食品ロス対策など、具体的なアイデアを発表することで、持続可能な社会についての理解が深まります。
隠岐体験学習の振り返り
授業の初めでは、海と日本プロジェクトinしまねが主催した「隠岐めしと歴史探険隊」の動画も上映されます。これは2025年7月に行われ、島根県内の小学5・6年生20人が参加した体験学習の様子を映し出したものです。児童たちは、地元の漁師さんから直接指導を受け、海の食材の歴史や現状を学びました。
この体験の中で、子どもたちは隠岐特産のイワノリの減少を知り、地元海産物の保護の重要性に目を向けることができました。こうした実体験を通じた学びが、くら寿司の出張授業での学びもより深いものにするのです。
イベント情報
出張授業は、11月13日(木)に宍道小学校の体育館で行われ、13時50分から15時25分に渡って実施されます。また、メディア向けの事前レクチャーも行われる予定です。さらに、松江市内の他の小学校でも同様の授業が実施される予定で、地域全体で子どもたちの学びを支援していく姿勢が伺えます。
この取り組みは、海と日本プロジェクトが進めている「美しく豊かな海を次世代に引き継ぐ」という目的とも調和しており、地域社会で環境問題に取り組む活動の好事例となるでしょう。推進される授業を通じて、子どもたちが持続可能な未来について考える機会を得られることを期待しています。



関連リンク
サードペディア百科事典: 海と日本プロジェクト くら寿司 隠岐めし
トピックス(イベント)


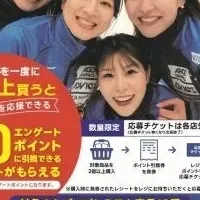
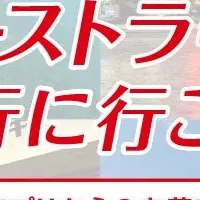




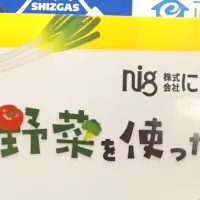
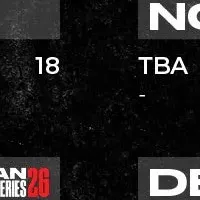
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。